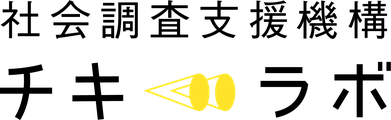今年は阪神淡路大震災から30年となります。そして今月(3月)で、東日本大震災から14年です。昨年は、「南海トラフ地震臨時情報」が初めて発信され、防災について改めて考える1年ともなりました。政府も防災庁の設置に向けて動き出しているところです。
今回のリサーチチームブログでは、「災害用備蓄」をテーマに第13回目の「社会抑うつ度」調査結果をご紹介します。また、自治体の備蓄状況の内閣府調査データも参考に、私たちが個人として備えるべきことは何かを考えていきたいと思います。
▽チキラボの「社会抑うつ度調査」の概要・調査手法・第13回調査の回答者の基本データは本記事の末尾に説明しています。▽
I . 備蓄行動への消極的な姿勢が目立つ結果に
チキラボの「社会抑うつ度」調査では、「災害に備えて、定期的に備蓄の点検と補充を行なっている」かとの質問を行いました。それに対し、「どちらかといえばあてはまる」「あてはまる」と回答した人は44.7%でした。まだ半分以上の人は、備蓄の点検や補充を行なっていないという状況がわかりました。
また、2024年の8月8日に「南海トラフ臨時情報」が発表された約1ヶ月後に実施したこの調査では、その情報を受けて「防災グッズを整理した」か、「防災グッズを買った」かについても質問しました。その結果、どちらについても、2割〜3割程度の人しか行動をしていなかったということもわかりました。

図1 チキラボ社会抑うつ度調査結果 防災関連
個人の備蓄行動は消極的な姿勢が目立つ……こんな状況が見えてきます。では自治体の備えはどうなっているのでしょう。
Ⅱ.主食の備蓄にも自治体格差
令和7年1月9日に、避難所の開設に備えた物資や資機材等の自治体の準備状況を点検した結果を内閣府が公表しています。この調査では、様々な食品や避難所に必要な備品の備蓄数が調べられていて、都道府県別、市区町村別の結果が公表されています。
その調査結果の中から、主食とアレルギー対応食の備蓄状況、そして乳幼児が必要とする物資の備蓄状況に注目してみたいと思います。
各自治体による調査結果は、自治体による備蓄総数を公表しただけなので、ここでは一人あたりの備蓄数を計算し、都道府県別に比較ができるようにしました。各都道府県の2024年の人口を『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査』から入手し、備蓄数を割っていきます。
まずは主食についての一人あたりの備蓄数の分布を確認しましょう。内閣府の調査では、主食はいくつかの品目に分けて、備蓄数が把握されています。主食類として調査されている品目は、以下の11品目です。
・主食類(※米・パン等)
・精米
・アルファ化米
・菓子パン
・惣菜パン
・カップの即席麺
・袋の即席麺
・乾パン
・おにぎり
・パックご飯(※約180g)
・缶詰(※主食)
このうち、精米以外は全て、「食」または「個」といった単位で数えられていました。わかりやすくするために、ここでは「個」や「食」を単位に把握されている品目の一人あたり備蓄数を合計した値の、都道府県別の結果をお示しします。これは、一人あたりどのくらいエネルギー量がある食事が備蓄されているのかを示すものではない点、ご注意ください。
色が濃い自治体ほど一人あたりの備蓄数が多いことを示しています。最大は高知県で一人当たり1.53(食/個)、ついで東京都の1.43(食/個)、静岡県の1.41(食/個)です。大規模災害が懸念されている都道府県で主食の備蓄数が比較的充実している様子がわかります。逆に備蓄数が最も少ないのが鳥取県で0.10(食/個)となっています。
注意してほしいのは、濃い赤色であるからと言って、これは絶対的に備蓄数が足りているということを意味するわけではありません。これはあくまで、「47都道府県の中では備蓄数が比較的多い」ということを意味しているのであり、さらなる見直しは必要です。

図2 一人あたりの主食備蓄数 都道府県別比較
さらに詳しく、都道府県別・品目別の一人あたり備蓄数を知りたい方はこちらのリンクから表をご覧ください。
なお、この地図には反映されていませんが、三重県はどは、おにぎりなど、調理のいらない食品の備蓄が充実している状況が確認でき、自治体間でその品揃えについても、格差があると言えそうです。
Ⅲ. 対応別れるアレルギー食、比較的充実の赤ちゃん物資
次に注目したのが、アレルギー対応食(主食)の備蓄状況です。ここにも自治体間に格差があることが確認できます。最多は宮城県の0.43食で、アレルギー対応食の備蓄に力を入れている様子がうかがわれます。一方で、限りなく0食に近い自治体が数多くあります。

図3 一人あたりのアレルギー対応主食備蓄数 都道府県別比較
さらに赤ちゃん用の物資についてもみていきましょう。こちらは、各都道府県の0歳児人口(推計)で、一人あたりの備蓄数を計算してみました。
液体ミルクや粉ミルクは「缶」や「本」単位で計上し、実際の合計容量で計上しているわけではないため、単純な比較は慎重に行う必要があります。

図4 一人あたりの粉ミルク・液体ミルク備蓄数 都道府県別比較
紙おむつの備蓄は比較的満遍ない充実度になっている様子がわかります。しかし、自治体間に差があることも確かです。

図5 一人あたりの紙オムツ備蓄数 都道府県別比較
さらに詳しく、都道府県別・品目別の一人あたり備蓄数を知りたい方はこちらのリンクから表をご覧ください。
Ⅳ.自治体の備蓄に期待しすぎない備えを
チキラボの「社会抑うつ度」調査では、備蓄行動に対する消極層が目立っていることを確認できました。もしかしたら、自治体の備蓄を頼りにしている方もいるかもしれません。
しかし、自治体の備蓄にも格差があること、アレルギー対応食などに対する備えにも温度差があることから、今はまだ、個人の備えがなければ、災害に脆弱な状況となってしまうと言えてしまいます。
政府は防災庁の設置に向けて、防災関連予算を増額し、地域の防災力強化を掲げているところです。自治体間の備蓄状況の格差是正に向けた動きを政府には強く求めたいですが、同時に、私たち自身も、自治体の備蓄の「現状」を知り、自己備蓄も合わせて取り組むことも必要となりそうです。
【参考文献】内閣府2025年1月9日『災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査結果』https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r6_1101.pdf
【謝辞】調査票の設計・実際・データ整理・集計表の作成、分析は大川明李さんにご協力をいただきました。
===
【チキラボ「社会抑うつ度調査」とは】
チキラボの「社会抑うつ度調査」では、人々の心理状態の推移を追いかけています。災害や景気、政治イベントやメディアイベントなどによって、メンタルヘルスがどう変化するのか。そのデータをもとに、自殺対策やメンタルケアをはじめとした、様々な対策・提言につなげていくことをチキラボでは目指しています。
調査手法は、株式会社アイブリッジのモニターを対象にしたウェブ調査となっております。一定の割り付けを行いつつ、ランダムサンプリングによって調査対象者を抽出しているため、日本社会の一般的傾向を推計できるデータとなっています。また、データの精度を少しでも上げるためにサティスファイス項目(文章を読んで回答しているかを尋ねる疑似質問)を設け、その質問をクリアできた回答者のみを「有効回答」とし、分析をしています。
本ブログに引用した第13回調査では株式会社アイブリッジが保有するモニターのうち、18〜79歳の男女1003名の回答を得ました。全国の地域・性別・年齢の人口分布に合わせて調査対象者の割付を行っています。最終的には2つのサティスファイス項目を通過した846名を有効回答とし、分析をしています。