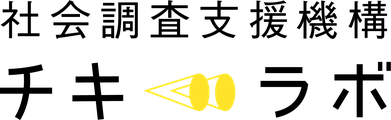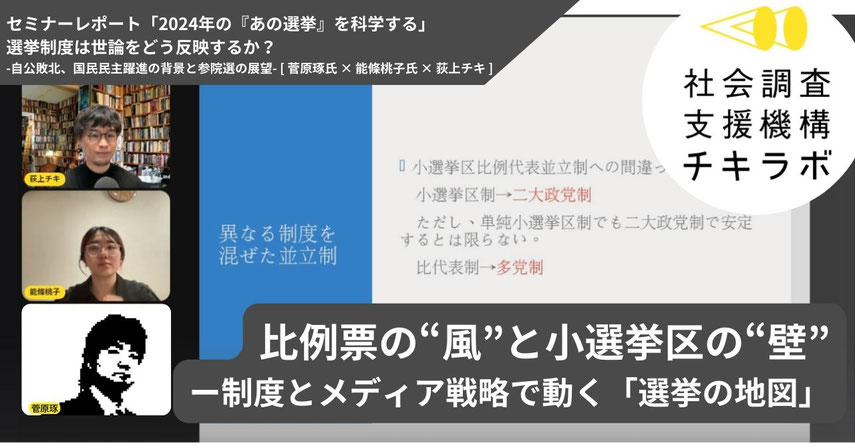
3月23日(日)、選挙振り返りセミナー「選挙制度は世論をどう反映するか?-自公敗北、国民民主躍進の背景と参院選の展望-」を開催。ゲストには、『選挙との対話』に論考を寄せ、過去2回のセミナーでも選挙制度の解説と選挙分析を解説していただいた菅原琢氏。そして、ジェンダー平等実現を目指して地方議会議員に立候補する20代・30代の女性(トランス女性を含む)やノンバイナリー、Xジェンダー等の方を支援するFIFTYS PROJECT代表の能條桃子氏をお迎えしました。
冒頭の菅原氏からのキースピーチでは、小選挙区比例代表並立制についてのおさらいと2024年衆院選で与党が過半数を割った要因の2つのテーマについて解説していただきました。トピックをご紹介します。
日本の選挙制度は世界的にも珍しい「小選挙区制と比例代表制の併用」
- 誤った期待「小選挙区制のもとでは、候補者の絞り込み効果が期待されるため二大政党制が生まれやすい」
- 多党制を促す比例代表制により、小さな政党もプレイヤーとして加わることが可能
- 2制度の併用によって、比例票を見込んで小選挙区に候補を立てる動きにより、候補者の絞り込みがうまく機能しなくなることがある
- このような制度の中では、政党間の協力によって統一候補を立てることが重要
- 既に出ている効率的な政党間協力の最適解「自公協力」
国民民主の「躍進」は本当か?—2024年衆院選報道と実情のギャップ
- 選挙区で自民党が大きく得票を減らし、立憲民主党が得票率を維持したことが選挙全体に大きな影響を与えた
- 立憲は共産党との協力がなかった分を、国民民主党との協力でカバーできた
- 国民民主党は比例区では一定の票を得たものの、小選挙区ではそれほど善戦できなかった
- 報道の印象と実態には乖離がある「国民民主党の躍進」
「立てるメリット」と「引く代替案」―野党共闘を進めるために必要な調整
能條さんからは、「共産党が小選挙区で候補を擁立しなければ、さらに立憲民主党の議席が伸びた可能性があるが、比例票にはどの程度影響があるか?」「小選挙区に候補を立てれば選挙カーやポスターが使えるという明確なメリットがある。立憲側が協力を得るにはその代替手段を提示する必要があるのでは」との問いかけがありました。
これにこたえて菅原氏からは、小選挙区への候補擁立で比例票が増える効果は一定程度見込めるものの、実際には限定的であること。それ以上に「運動を維持する」という目的で候補を立てるケースが多いとの指摘。
また、共産党が小選挙区で候補を立てないことは、与野党逆転の可能性を高める一方、党にとっては非常に難しい判断であることにも言及。その上で、共産党としても立憲民主党とある程度の協力関係を築くことは、マスメディアや人々の中での存在感を高めることにつながり、結果として党の影響力を強めることにもなりうる、との見解が示されました。
ネットの風が国民民主党を押し上げた、というストーリーは本当か?
荻上からの問いは、「無党派層や若者、ネットの風が国民民主党を押し上げたというストーリーは本当か?」というものでした。
菅原さんは、国民民主党がネットを中心に自民党の若年層支持者の一部を取り込んだことが、比例での得票増につながったと分析。ただし、そのリーチは限定的で、他党の支持層から広く票を奪うには至っていないと指摘されていました。
他方でGoogle広告での露出などの様子から、国民民主党の現役世代への給付を訴える広告戦略が非常に効果的に機能した側面も。
この点について能條さんも、国民民主党の広報戦略の巧みさに言及。世論調査の前に意図的に露出を増やすことで、「支持がありそうだ」という期待感の醸成に成功したことが、得票に寄与した大きな要因だったと重ねて指摘がありました。
支持を集める「政党の実力」とは?
後半の質疑応答のパートでは、参加者の方からの「政党が支持を集める“実力”とは何か?」という根本的な問いをいただきました。
菅原さんは、国民民主党が打ち出した「現役世代の手取りを増やす」という明確なメッセージを例に挙げながら、「国民全体のため」よりも「あなたのことを考えている」という訴えのほうが、支持につながりやすいと指摘しました。
つまり、「この政党なら自分の味方になってくれる」と感じさせるブランドを確立し、有利な政策を実現してくれるという信頼や期待をいかに醸成できるかがカギ。そのためには、「誰のための政党か」を明確にすることが重要だと述べました。
さらに、かつては70%あった投票率が現在は50%前後にまで落ち込んでいる現状に触れ、「有権者の2割が選挙そのものから撤退している」との見方を提示。若者や無党派層、政治への関心を失った層へのリーチは、政界全体にとっての大きな課題であるという認識が共有されました。